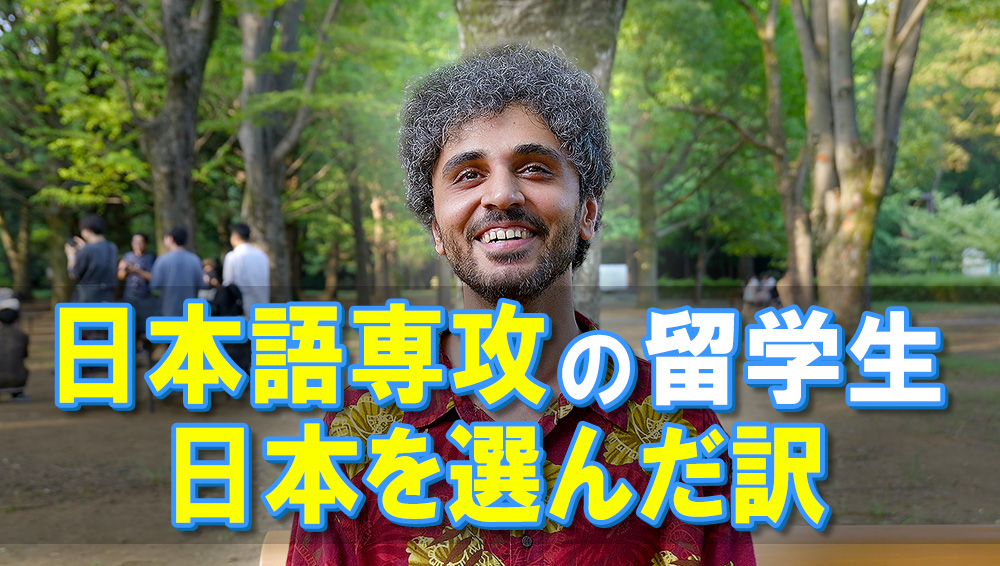外国人にインタビュー第4弾!
今回はつい最近来日した、日本語が堪能なイラン人留学生にインタビューしました!
今回の来日は2回目だということで、
〇 なぜ日本に興味を思ったのか
〇 日本での思い出
〇 好きな日本の有名人
〇 おもしろい日本語
などなど、様々な質問を日本語で聞きました!
フルバージョンはYouTubeに動画をアップしています。
それでは早速いってみよう!
- イランで日本語を専攻!
- 好きな日本人は?
- イランで有名な日本人は「おしん」!
- 日本でのカルチャーショック
- 日本でまさかのアクシデント!!
- おもしろい日本語は「ちゃらんぽらん」
- まとめ
- 国境を越える愛:多文化ぐらし夫婦が語る国際結婚のリアルと成功の秘訣
イランで日本語を専攻!
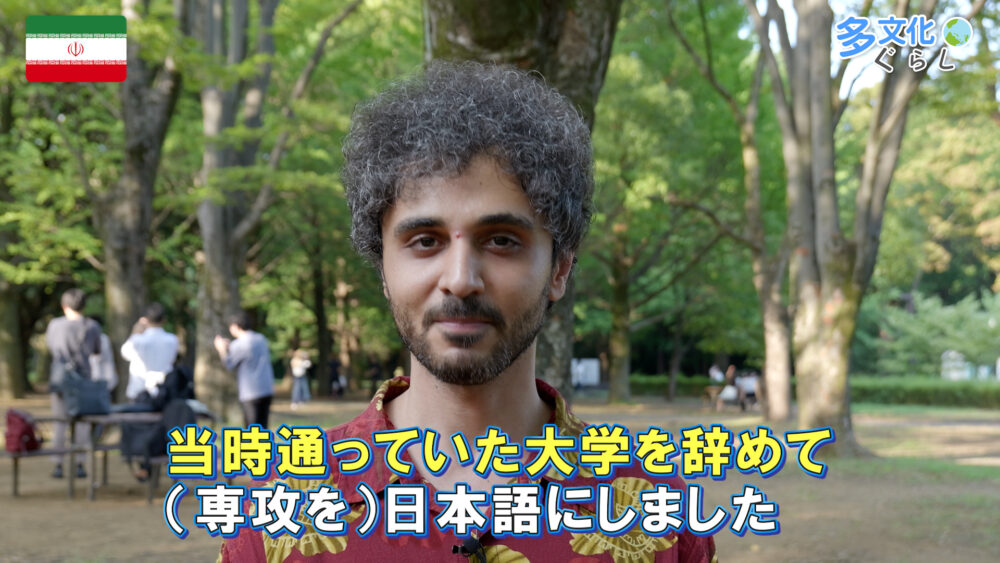
まず気になるのがどうしてイランで日本語を勉強しようと思ったのか。
もともとは大学で英語を専攻していたそうですが、イランの最難関大学といわれるテヘラン大学に入りなおして日本語を専攻することにしたそうです!
日本との出会いは高校生の時にアニメを観たこと!ナルトやブリーチを見て日本に興味がわいたそうです。
その後、日本の50・60年代の映画にも触れ、
➤ 黒澤明
➤ 溝口健司
➤ 大島渚
などの映画監督の作品も観て、
日本語で映像作品を観たいと思って日本語を専攻する決意をしたそうです。
とはいってもすでに別の専攻で大学に進学していました。
それでも日本語への情熱を抑えることはできず、受験勉強を経てイラン最難関大学に入学しました。
今では日本語学習歴5年で、流暢に日本語で話せるようになっています。
YouTubeで動画版を観てもらうと分かるよ!アニメや映画の力はすごいですね!
好きな日本人は?

好きな日本人は、映画監督の大島渚氏とワンピース作者の尾田栄一郎氏だそうです。
日本語との出会いがアニメと映画だったので、2人のことが特に好きだそうです。
尾田栄一郎氏の人気はすごいですね。ほかの国の方にもファンがとても多い印象です。
イランで有名な日本人は「おしん」!
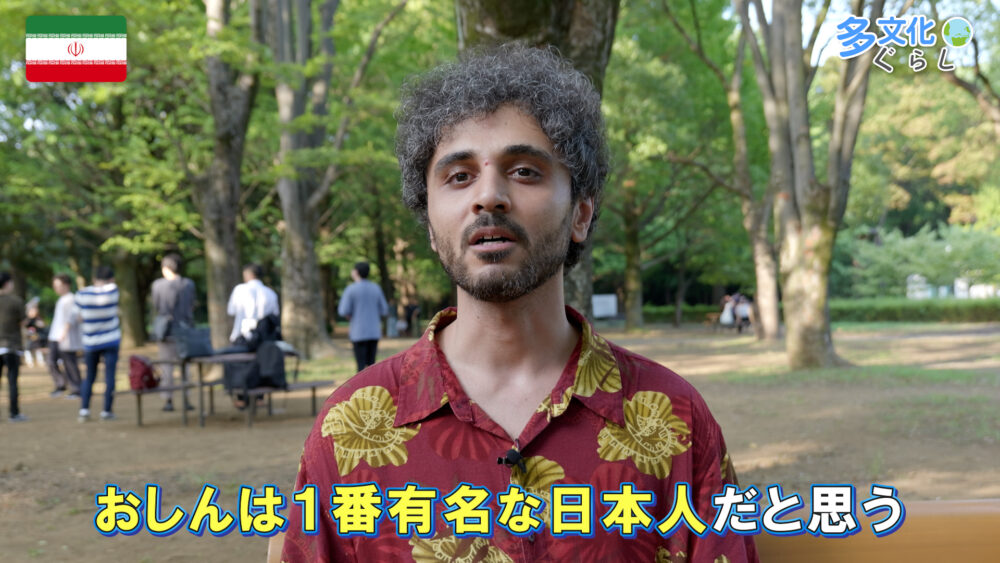
イランで有名な日本人は意外にも「おしん」だそうです。
日本だと割と上の世代でないと知らない人も多いかもしれませんね。
イランで「おしん」が放送された際に、多くのイラン人の心をつかんだようです。
私もイランに行ったとき、私が日本人だと分かると「おしん!おしん!」と言われたことが何回もあります(笑)
年配の世代だけでなく、若い世代にも認知されているのもすごいです。
若い世代は日本の俳優や漫画家が人気だそうですが、彼の世代では日本人といえば「おしん」だそうです。
日本でのカルチャーショック
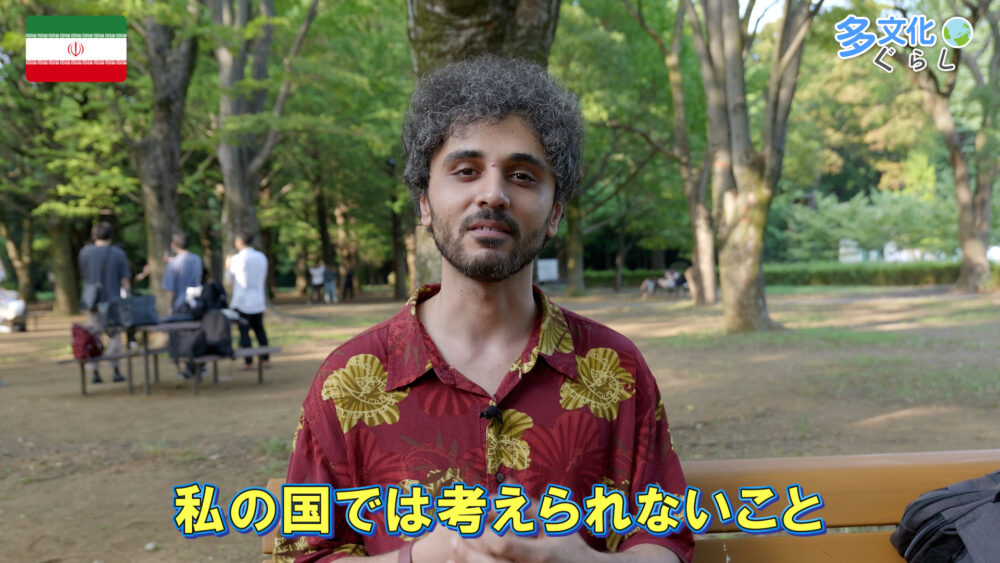
日本好きな彼が日本で感じたカルチャーショックはあるのでしょうか?
イランと日本にはやはり様々な違いがあり、彼もカルチャーショックをいくつか感じたことがあるそうです。
ゴミ箱ないっ!
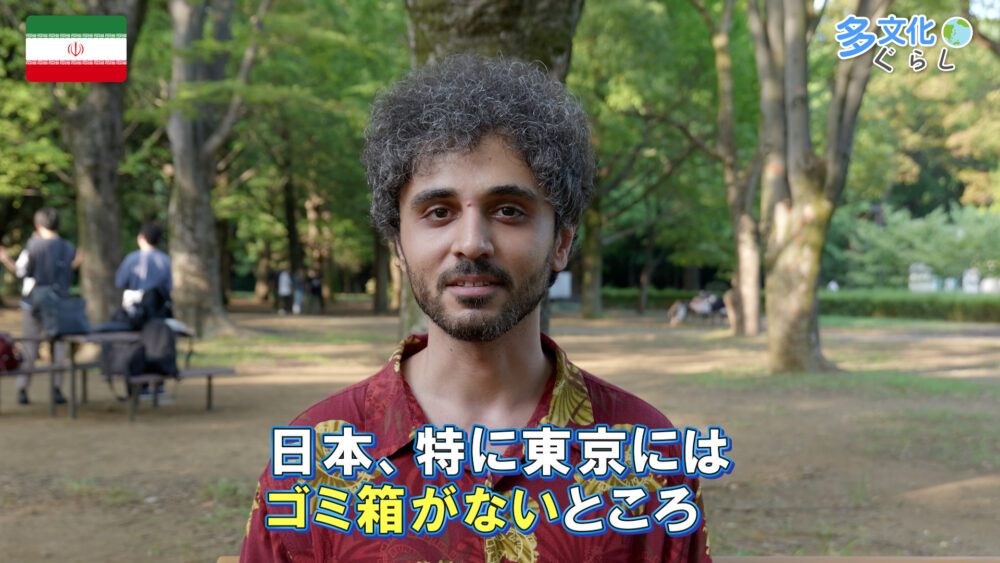
まずゴミ箱が少ない!
特に東京ではコンビニで買い物をして出たゴミを家に帰るまでバッグに詰めておかなければならないので大変だと感じたそうです。
確かにゴミ箱少ないかもしれませんが、あったらあったで異臭が出たり虫が湧いたりして不衛生になりそうですけどね。どっちをとるかですね…
コンビニのセクシー雑誌

2つ目は、コンビニに堂々と置かれているセクシー雑誌!
これは日本特有かもしれませんね。
イスラームが政治の中心となっている現在のイランでは考えられないことなので驚いたそうです。
子供でも誰でも見えるところに性的なものを置くことに、違和感を覚える外国人はとても多いです。
売れてるから置いてるんでしょうけど…コンビニにある必要あるんですかね…
真冬のコスプレイヤー
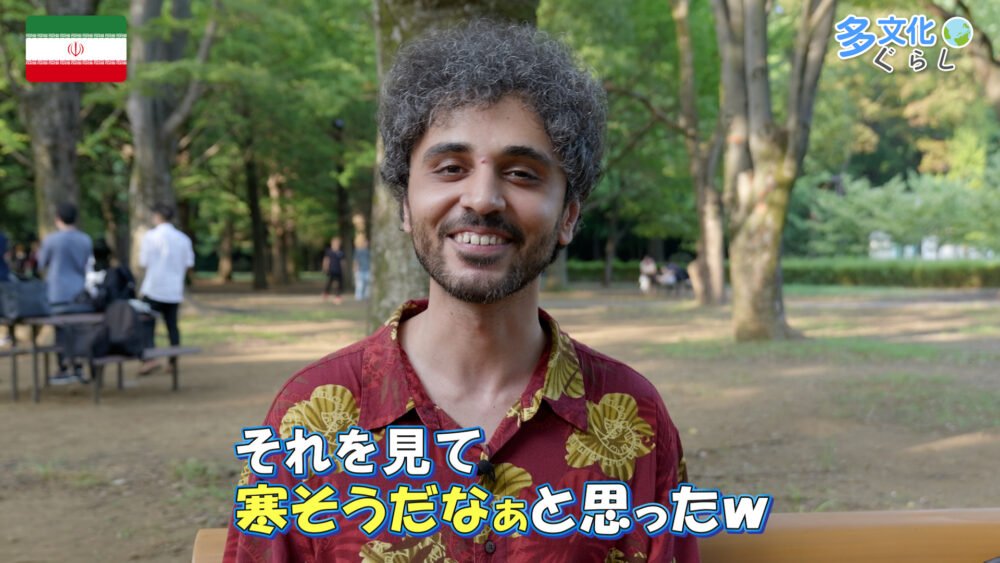
3つ目は真冬のコスプレイヤーの服装!
とある冬のフェスティバルでコスプレイヤーを見かけたそうですが
驚いたのはコスプレイヤーそのものというよりも、その衣装!
真冬で寒いのに露出度が高い服を着て歩いていたそうです。
日本のコスプレイヤーの熱量に驚くと共に、
寒そうだなぁと心配になったそうです(笑)
日本でまさかのアクシデント!!
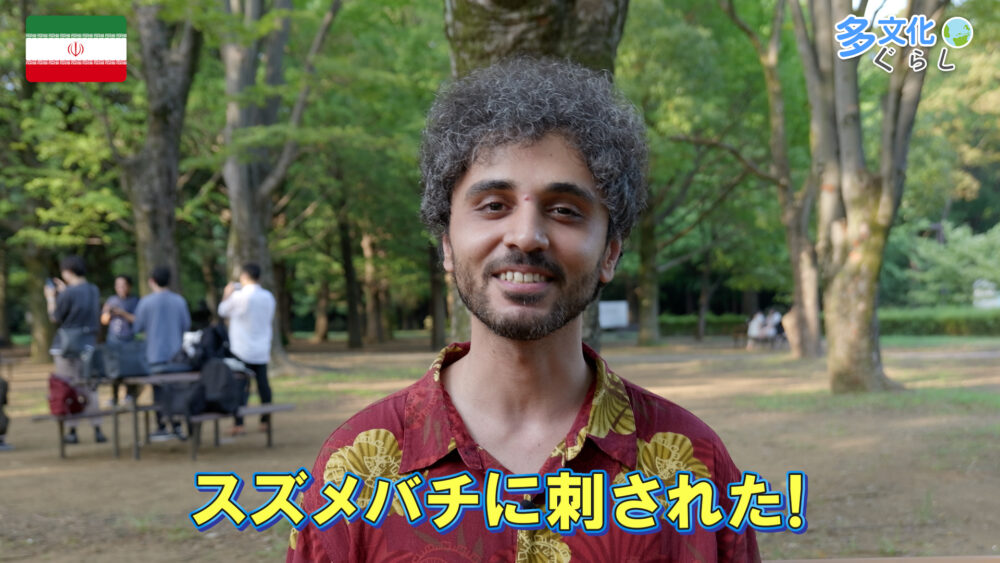
日本での悪い思い出は、スズメバチに刺されたこと!
何気なくいつものように道を歩いていたらスズメバチに刺されたそうです。
1ヵ月ほどかゆみと痛みがあって死ぬかと思ったみたい。
一般的に日本には虫が多く、虫が嫌いな彼にとっては日本での生活のデメリットになっているとのこと。
日本人でもそうそうスズメバチに刺される経験をすることはないですが、以前の1年の滞在で早速経験しているところは運が悪かったですね…
おもしろい日本語は「ちゃらんぽらん」
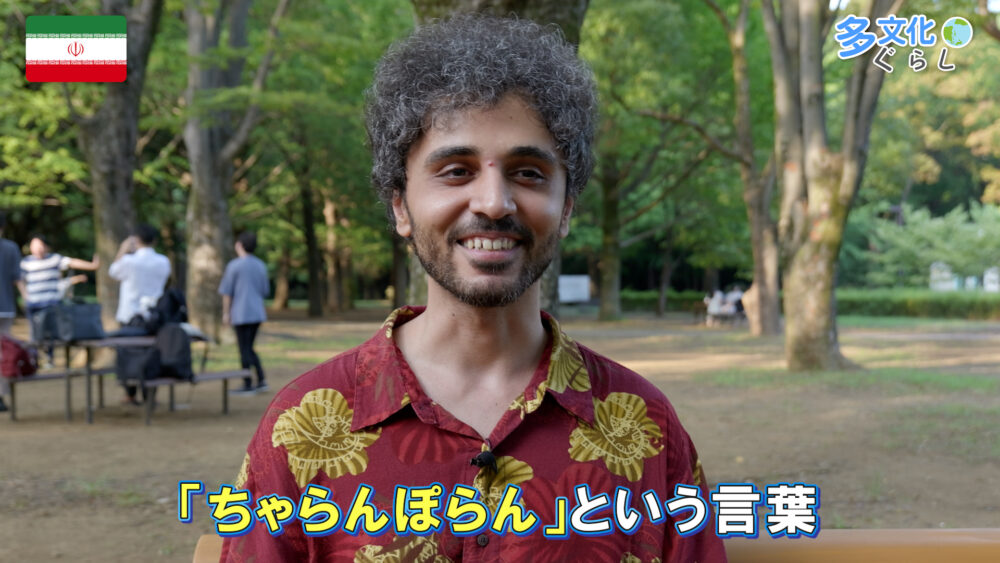
日本語を専攻しているとのことだったので、イランの公用語であるペルシア語と似ている日本語がないか聞いてみました。
「ちゃらんぽらん」という単語がペルシア語の単語と発音と意味がそっくりだそうです。
他におもしろいと思った日本語は、大阪弁!
大阪弁にはおもしろい単語や文章が多いと感じているそうで、
特におもしろいと思った単語は「しばくぞ!」
どこで聞いたんでしょう(笑)…
まとめ

いかがだったでしょうか?
アニメや映画で日本に興味を持って、通っていた大学を辞めて日本語に専攻を変えて5年。
様々なカルチャーショックを感じたり、スズメバチに刺されたりもしながら
大好きな大島渚と尾田栄一郎の生まれた日本で日本語を勉強しています。
日本への留学も実現した彼が、日本でこれからもいい思い出を作っていければいいですね!
国境を越える愛:多文化ぐらし夫婦が語る国際結婚のリアルと成功の秘訣
皆さん、こんにちは!「多文化ぐらし」を運営してるぐらです。
私はイラン人の妻と国際結婚して、毎日異文化ぐらしを満喫しています。
今回は、私自身の経験も踏まえながら、みんなが気になってるであろう国際結婚のリアルと成功のコツについて、ぶっちゃけ話をしちゃいます!
国際恋愛や国際結婚に興味はあるけど、なんか漠然と不安…って人、いるよね?もう国際結婚してるけど、毎日ちょっとした壁にぶつかって悩んでる…って人もいるかもしれない。この記事を読めば、みんなの疑問や不安がスッキリ解消されて、前向きな気持ちになれるはずだよ!
【実体験から学ぶ】多文化ぐらし夫婦が語る国際結婚の魅力と現実
私たちはイランで出会って、3年間の遠距離恋愛を経て結婚に至りました。遠距離って正直、楽な道じゃなかったけど、お互いの文化を理解して尊重し合う気持ちがあったから、国境を越えた愛を育てられたんだよね。
国際結婚して本当によかったこと、マジで山ほどあるんだ。違う文化を持つ相手と暮らすって、自分の常識がひっくり返るような体験の連続で、毎日が新しい発見で楽しんですよ。
妻のイラン文化に触れるたびに「へぇ〜!」って驚かされて、人生がどんどん豊かになっていく感じ。異文化交流って、最高の学びだなって実感してる。
でもね、もちろん国際結婚にしかない「壁」も存在する。その壁を二人で力を合わせて乗り越えられたら、日本人同士の結婚よりもっと強く、もっと豊かな絆が生まれるって信じてるよ。
離婚率の噂ってホント?数字の裏にある「違い」との付き合い方
国際結婚って聞くと、よく「離婚率が高いんでしょ?」って言われるよね。私も結婚前にそういう情報を見て、ちょっとドキドキしたことがあります。
でも実は、この離婚率に関するデータって、すごくややこしくて矛盾してることもあるんです!
データに騙されちゃダメ!
「国際結婚の離婚率は国内結婚より高い」って言うデータもあれば、逆に「国際結婚の離婚率のほうが低い」っていうデータもある。これって、どっちが本当なの?って混乱するよね。
この大きな食い違いは、主に計算の仕方が違うからなんだ。
例えば、その年に結婚したカップルと、離婚したカップルを単純に比べただけのデータは、実際の状況を正確に表してるわけじゃない。メディアで「国際結婚の離婚率50%超!」みたいなセンセーショナルな見出しを見かけるけど、あれはちょっと大げさなことが多いんだ。
もちろん、どの国のパートナーと結婚するかによって離婚率は違うし、文化的な近さとか、ジェンダーの役割に対する考え方、経済的なことなんかが複雑に絡み合ってる。
でも、一番大事なのは、数字に一喜一憂しないこと! 私自身、国際結婚をしてるからこそ思うけど、大切なのは数字の裏にある「違い」をどう受け入れて、どう向き合っていくかだよ。
国際結婚の成功って、ただ離婚しないってことだけじゃない。お互いが満足できて、ケンカしてもちゃんと仲直りできて、二人の文化が混ざり合って、独自の「第三の文化」を創り出していくことだと思う。
つまり、文化的な違いを乗り越えるだけじゃなく、それを二人で楽しめるようになれば最高ってこと!
文化の壁を乗り越える:国際結婚でぶち当たるコアな問題
国際結婚で避けて通れないのが、やっぱり「文化の壁」。壮大な価値観の違いだけじゃなく、日常生活の些細な場面にも現れて、たまに大きなストレスになるんだ。
コミュニケーションの断絶:空気を読む文化 vs. ズバッと言う文化
国際結婚で一番の課題は、コミュニケーションのスタイルが根本的に違うこと。
文化人類学者のエドワード・T・ホールって人が言ってるんだけど、日本は「空気を読む」ハイコンテクストな文化。言葉にしなくても、相手の気持ちを察するってことが大事にされるよね。一方、アメリカやドイツ、北欧なんかは、メッセージを明確に、直接的に言葉で伝える「ローコンテクスト」な文化なんだ。
この違い、実生活で深刻な誤解を生むことがある。例えば、私が「検討するね」って言ったのを、妻は「OKなんだ!」って勘違いしたり、逆に妻がハッキリ「ノー」って言ったのを、私が「ちょっとキツイな…」って感じたり。
でも、これを乗り越えるために私たちが意識したのは、「何でも言葉で伝える」こと。
相手の言葉で分からない部分があったら、そのままにせず、「それってどういう意味?」って素直に聞くようにしてる。完璧に流暢じゃなくても、「あなたの文化を理解したい」って気持ちを言葉や行動で示すことが、信頼関係を深める上でめちゃくちゃ効果的だと感じてるよ。
価値観の衝突:家族、ジェンダー、お金
コミュニケーションスタイルの違いに加えて、具体的な価値観の衝突も国際結婚の大きなストレス要因になるんだ。
- 家族と義理の親族:家族の距離感に関する考え方は文化によって全然違う。
義理の親とどれくらいの頻度で会うか、親の介護をどう考えるか、なんてことが対立の原因になりがちだね。 - ジェンダーの役割と家事分担:家事の分担についても、考え方は衝突しやすい。
多くの西洋文化では平等に分担するけど、伝統的な性別役割分業が根強く残ってる文化圏もある。専業主婦(主夫)の考え方とか、掃除の基準なんかも問題になることがある。 - お金の価値観:金銭問題は、一番深刻な対立の原因の一つ。
将来のために貯金する文化と、今の楽しみを優先する文化の違いとかね。特に、母国の家族に仕送りする義務がある場合、大きな緊張の原因になり得る。
ぐらの経験談:お金や家族との向き合い方
私たち夫婦も、お金の使い方や家族との付き合い方について、よく話し合ってる。イランの文化では、家族の絆がめちゃくちゃ強いんだ。最初は、その距離感や金銭に関する考え方に戸惑うこともあったけど、お互いの文化を理解しようと努めて、「何が大切なのか」を話し合うことで、バランスの取れた関係を築けるようになった。大事なのは、一方の価値観を押し付けるんじゃなくて、二人にとって最適な**「ルール」を一緒に作っていくこと**なんだ。
日常の「常識」が衝突する時
文化的な違いは、壮大な価値観だけじゃなく、ごく普通の日常生活にも現れて、それが繰り返されると大きなストレスになる。
- 食生活:イラン料理はスパイスが効いて濃厚な味付けが多いけど、日本の和食は繊細な出汁の味を大切にする。最初は、お互いの料理が「味が薄い」「味が濃すぎる」って感じたこともあったね。
- 住環境:部屋の明るさの好みや室温の感覚なんかも違う。来客のもてなし方についても、文化による違いをたくさん感じる。これらの小さな違いは、毎日起こるからこそ「またか…」とストレスになりがち。でも、私たちが心がけているのは、「これは文化の違いだ」と認識して、相手を非難しないこと。そして、「どうすればお互いが快適に過ごせるか」を話し合って、妥協点を見つけること。例えば、料理は交代で作ったり、相手の好みに合わせて味付けを調整したり。そうすることで、私たち独自の「多文化ぐらし」の日常が生まれていくんだ。
国境を越えた子育て:バイカルチュラルな家族形成の複雑性
国際結婚家庭における子育ては、日本人同士の結婚とは違う、ユニークな複雑さを伴う。もし将来子供を授かったら、私たち夫婦もこの課題に直面するだろうね。
バイリンガルという綱渡り
国際結婚家庭の子育てでユニークな課題が、言語教育。多くの家庭では、バイリンガルの子供を育てるために「一人一言語(OPOL)」の原則を採用する。これは、親それぞれが自分の母国語だけで子供に話しかける方法のことをいいます。
でも、これって意外と難しいそうです。
子供が生活する社会の主要言語(日本なら日本語)が、もう一方の少数派言語を圧倒しちゃうことが多い。もし慎重にやらないと、どっちの言語も中途半端になっちゃう「セミリンガル」になるリスクもある。
価値観の衝突:しつけ、教育、自立
子育てに関する価値観の相違は、言語以上に深刻な対立を生む可能性があります。
- しつけと自律性:子育てのスタイルは文化によって全然違う。
アメリカでは幼い頃から自立を促すけど、日本ではより指示的なアプローチが一般的。 - 教育への期待:高等教育に対する親の経済的責任についても考え方が違う。
欧米では「親が学費を出すのは高校まで」っていう考えが強い国もあって、これが夫婦間の対立の原因になることもあるんだ。
アイデンティティの形成:「サードカルチャーキッズ(TCK)」の経験
両親の文化とも、住んでる国の文化とも違う環境で育つ子供たちは、「サードカルチャーキッズ(TCK)」って呼ばれてる。
複数の文化に精通してるっていう強みを持つ一方で、どの文化にも完全には属していない感覚、つまり「アイデンティティクライシス」に直面することもある。
だから、TCKを育てるってことは、親自身が「自分の文化のどの部分を子供に伝えるのが一番大切か?」っていう、根本的な問いに向き合わざるを得なくなる。このプロセスは大変だけど、うまく乗り越えられたら、親としての絆がさらに深まるチャンスにもなるんだそう。
ぐらの視点:子供の教育とアイデンティティへの考え
私たち夫婦はまだ子供はいないけど、将来子供を持った時の子育てについてはよく話し合ってる。やっぱり、子供がどっちの言語を第一言語にするか、二つの文化の中でどうやってアイデンティティを形成していくかは大きな関心事だね。
私たちは、子供が両方の文化の良い部分を吸収して、それを自分の強みとして生かせるような環境を作ってあげたいと思ってる。そのためには、親である私たちが、まずお互いの文化を深く理解して尊重し合う姿勢を見せることが一番重要だと感じてる。子供が「日本人らしさ」や「イラン人らしさ」に悩んだ時に、両親が協力して「家族としての文化」を提示できるような関係性を築いていきたいね。
外部からの圧力:社会と制度がもたらす試練
国際結婚カップルは、文化的な違いとは別に、社会や制度的なストレスにも直面する。これは、日本人同士の結婚にはない、国際結婚特有の「ストレス税」みたいなものです。
官僚制度の迷宮:ビザがもたらす心理的負担
国際結婚カップルが一番ぶつかるのが、在留資格(配偶者ビザ)の取得と更新に伴う膨大な手続き、将来への不安、そして心理的ストレスです。
このプロセスは一度きりじゃなくて、定期的に繰り返される不安の源なんだ。更新のたびに、安定した結婚生活を送っていることを証明しなきゃいけない。このプレッシャーは、カップルの日常生活に重くのしかかる。
社会的試練:家族の反対と社会の偏見
- 家族の承認:国際結婚カップルの約半数が、親からの反対という最初の関門に直面すると言われてる。
- 偏見とマイクロアグレッション:社会における「目に見えるマイノリティ」として生活することは、さらなるストレスを生む。
「日本語がお上手ですね」なんて、一見褒め言葉のようで、相手を非日本人として区別する発言がこれにあたる。こういう経験は、孤独感や疎外感につながる可能性がある。 - 法的迷宮:相続、税務、国籍:国境を越えた相続は、めちゃくちゃ複雑。
どの国の法律が適用されるかとか、専門的な知識がないと乗り越えられない壁がたくさんある。 - 二拠点生活と税務:二つの国を行き来するカップルは、二重課税のリスクに直面する。
適切な申告には、国際税務に詳しい専門家のアドバイスが不可欠。 - 子供の国籍:子供のために二重国籍を確保する手続きも複雑で、時間的な制約もある。
これらの外部からの圧力は、関係性への「ストレス税」として機能しているようなものです。日本人同士のカップルが、二人の関係性や仕事にエネルギーを注げるのに対して、国際結婚カップルは、それに加えてビザの管理、偏見との闘い、そして複雑な法律問題に対処するための時間、お金、感情的なエネルギーを支払わなきゃいけないんだ。
ぐらの経験談:ビザや社会の目に直面した時のこと
幸いなことに、私と妻はビザの取得や更新で大きなトラブルはなかった。
でも、その手続きの複雑さや、将来への不安は確かに感じたな。社会の偏見やマイクロアグレッションについても、私自身が直接経験することはなくても、妻がそういった目に遭う可能性は常に意識してる。
私たちが心がけているのは、「自分たちは一人じゃない」っていう意識を持つこと。
同じ境遇の国際結婚カップルとSNSで繋がって、情報交換したり、共感し合ったりすることは、孤独感を軽減し、実践的なアドバイスを得る上でもめちゃくちゃ有効です。
もし深刻な問題に直面した場合は、専門家の助けを迷わず借りることも大切だと思います。
国際結婚を成功させるコツ:多文化ぐらし夫婦が実践してきたこと
国際結婚の成否は、挑戦がないことじゃなくて、それらの挑戦にどう向き合って、どう乗り越えていくかにかかってるってことが、よく分かったんじゃないかな。
基本的な心構え:「違いがデフォルト」という認識
成功してる国際結婚カップルは、ただ違いを「許容」するだけじゃなく、それを関係性の基本として受け入れてる。
「違っていて当たり前」っていうこの考え方は、目標を「違いをなくすこと」から、「違いを乗り越えるための方法を二人で一緒に作っていくこと」へと変えてくれる。
不満は好奇心に変わり、対立は学びと成長のチャンスになります。
ぐらから見た:「違い」を楽しむ心の持ち方
私たち夫婦も、まさにこの「違いがデフォルト」っていう考え方を大切にしてる。
私と妻は、生まれ育った国も文化も言語も違う。だからこそ、お互いの「当たり前」が違うのは当然のこと。
この認識を持つだけで、衝突が起きた時に「なんで分かってくれないんだ」って感情的になるんじゃなく、「ああ、これも文化の違いか」って冷静に受け止められるんだ。そして、その違いをネガティブに捉えるんじゃなく、「二人で新しい、面白い解決策を見つけよう!」っていうポジティブな好奇心に変えるようにしてる。
積極的な設計:コミュニケーションの「第三の文化」を築く
成功するカップルは、どちらか一方の文化に頼るんじゃなくて、自分たち独自のルールと期待を明確に話し合って作っていく。この「第三の文化」の創造には、以下のことが含まれます。
- オープンで粘り強い話し合い:日常の些細なイライラから人生の大きな目標まで、何でも定期的に話し合う時間を持つことが不可欠。
- 言語への努力:完璧な流暢さを目指すんじゃなく、相手をリスペクトするため、そしてより深い繋がりを得るためのツールとして、お互いが相手の言語を学ぶ努力をすることが、信頼関係を深める上でめちゃくちゃ効果的。
- 対立を個人的な問題にしない:相手の行動が個人的な欠点じゃなくて、文化的な背景に基づいている可能性があると理解すること。これによって、非難し合うことを避け、建設的な問題解決へと進めることができるんだ。
ぐらが実践する「多文化ぐらし」流コミュニケーション術
私たちは、毎日小さなことでも話し合う時間を設けるようにしてる。何か気になることがあれば、「今話せる?」って確認してから、お互いの意見をじっくり聞くように心がけてる。その際、「これは、相手の文化ではこういう意味合いがあるのかな?」って一歩引いて考えるようにすると、感情的にならずに済むんだ。
また、お互いの言語学習への努力も欠かせない。妻は日本語を、私も彼女の母語であるペルシャ語を学び続けてる。完璧じゃなくても、「あなたの文化を理解したい」って気持ちを言葉や行動で示すことが、何よりも大切だと感じてる。
究極の成功要因:文化を超えた人間性
文化的な理解は欠かせないけど、長期的な成功は最終的に、結婚全体に関する研究で言われてる普遍的な人間性の資質にかかってるんだ。これには、柔軟性、共感力、コミットメント、共通のユーモアのセンス、そして短期的な「勝ち」よりもパートナーシップの長期的な健全性を優先する能力が含まれる。文化は対立と理解の文脈を提供するけど、最終的な結果を決定するのは、一人ひとりの人間性なんだ。
結論:進化する異文化間の結合
今回の分析から、国際結婚の成功は、挑戦がないことじゃなくて、それらの挑戦にどう向き合って、どう乗り越えていくかにかかってるってことが明らかになったね。
統計的な離婚率は、文化的背景や社会制度の複雑な相互作用を反映していて、個々のカップルの運命を予測するものではない。
成功の鍵は、コミュニケーションの断絶を埋め、価値観の衝突を乗り越え、子育てに関する独自の哲学を二人で作り上げて、そして社会からのプレッシャーをうまく管理することにあるんだ。
国際結婚を取り巻く環境は、これからも変化し続けるだろうね。リモートワークの普及は、場所にとらわれない柔軟な暮らしを可能にする一方で、新たな課題も生み出すかもしれない。
でも、国際結婚を成功させるために必要なスキル、つまり深い共感力、洗練された異文化コミュニケーション能力、柔軟な思考力、そして複数の視点を同時に持てる能力は、ますます複雑化していくこの世界を生き抜くために不可欠なスキルなのでないかな。
私自身、イラン人妻との「多文化ぐらし」を通して、毎日が学びであり、発見であり、そして何よりも大きな喜びだと感じています。もちろん、大変なこともあるけど、それら全てを乗り越えることで、より深く、より豊かな愛が育まれると信じています!
このサイト「多文化ぐらし」では、国際結婚や異文化について、これからも楽しく発信していくから、もし国際恋愛や国際結婚についてもっと知りたい方は、ぜひ他の記事もチェックしてみてね。YouTubeでも情報発信してるから、よかったらそっちもフォローしてね!
みんなの国際結婚生活が、より豊かで幸せなものになるよう、心から願ってるよ!
ぐらでした!
多文化ぐらしの最新記事もチェック!